INFORMATION FROM KATAKAGO KINDERGARTEN
2025年 6月の園だより
バックナンバー
- 2025年 5月
- 2025年 4月
- 2025年 3月
- 2025年 1月
- 2024年 11月
- 2024年 7月
- 2024年 6月
- 2024年 5月
- 2024年 4月
- 2024年 2月
- 2024年 1月
- 2023年 12月
- 2023年 11月
- 2023年 6月
- 2023年 4月
- 2023年 3月
- 2023年 1月
- 2022年 11月
- 2022年 10月
- 2022年 9月
- 2022年 8月
- 2022年 7月
- 2022年 6月
- 2022年 5月
- 2022年 4月
- 2021年 11月
- 2021年 10月
- 2021年 9月
- 2021年 5月
- 2021年 4月
- 2021年 3月
- 2020年 12月
- 2020年 11月
- 2020年 10月
- 2020年 9月
- 2020年 7月
- 2020年 6月
- 2020年 5月
- 2020年 4月
- 2020年 1月
- 2019年 12月
- 2019年 10月
- 2019年 7月
- 2019年 6月
- 2019年 5月
- 2019年 4月
- 2019年 3月
- 2019年 2月
- 2018年 10月
- 2018年 9月
- 2018年 5月
- 2018年 4月
- 2018年 1月
- 2017年 12月
- 2017年 11月
- 2017年 10月
- 2017年 9月
- 2017年 7月
- 2017年 6月
- 2017年 5月
- 2017年 4月
- 2017年 3月
- 2017年 2月
- 2017年 1月
- 2016年 12月
- 2016年 9月
- 2016年 6月
- 2016年 4月
- 2016年 3月
- 2016年 2月
- 2015年 11月
- 2015年 10月
- 2015年 7月
- 2015年 3月
- 2014年 11月
- 2014年 9月
- 2014年 7月
- 2014年 6月
- 2014年 2月
- 2014年 1月
- 2013年 10月
- 2013年 9月
- 2013年 7月
- 2013年 6月
- 2013年 5月
- 2013年 4月
- 2013年 3月
- 2013年 2月
- 2013年 1月
- 2012年 12月
- 2012年 10月
- 2012年 9月
- 2012年 7月
- 2012年 6月
- 2012年 5月
- 2012年 4月
- 2012年 3月
- 2012年 2月
- 2012年 1月
- 2011年 12月
- 2011年 11月
- 2011年 10月
- 2011年 9月
- 2011年 7月
- 2011年 6月
- 2011年 5月
- 2011年 4月
- 2011年 3月
- 2011年 2月
- 2011年 1月
- 2010年 12月
- 2010年 11月
- 2010年 10月
- 2010年 9月
- 2010年 7月
- 2010年 6月
- 2010年 5月
- 2010年 4月
- 2010年 3月
- 2010年 2月
- 2010年 1月
- 2009年 12月
- 2009年 11月
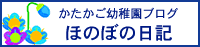

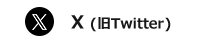


1.妊娠期の食事
1)避けたい4大危険物:①環境ホルモン、②有害ミネラル、③トランス脂肪酸が含まれる食品、④遺伝子組み換え食品:①は性ホルモンに影響、②は神経細胞ストップ、発育不良、自閉症の原因、③はパン、クッキー、ドレッシング、マヨネーズ、コーヒーフレッシュなどに含まれ、沢山摂ると、心身に健康問題を起こし、妊婦の場合、低体重や流産、死産の恐れあり、④は胎児、乳幼児、子どもへの影響が深刻。
2)積極的に摂りたいオメガ3:くるみ、青背の魚、亜麻の種に含まれ、赤ちゃんの脳や神経細胞の材料となり、思考力・記憶力がアップし、アレルギーの低減にも役立つ。
2.乳児期の食事(お母さん自身が穀菜食を摂る。赤ちゃんの脳や目が正常に発達)
母乳のメリット9:消化しやすい、腸の健康を高める、アレルギー性になりにくい、噛む力のベースになる、感染症にかかりにくい、母子の絆を深める、精神を安定させる、子宮からの出血を減らす、母体の産後の修復を促す。 母乳に含まれるタウリンは貝類、イカ、タコ、小型の青魚からも摂れる。
3.幼児期の食事=4つの大原則
1)食性にかなったものを摂る → 穀物:野菜・果物:魚・肉 = 5:2:1で摂る。
パン・麺類 → 食品添加物のリスクあり ごはん → 噛む習慣にもなる
牛乳にカルシウム:マグネシウムが11:1で含まれ マグネシウム不足になり骨がもろくなる。→ カルシウムとマグネシウムのバランスがとれている玄米、青菜、大豆で不足を補う。
マグネシウム不足:細胞や血管内でカルシウムが固まり、動脈硬化の原因になる。
イライラする、疲れやすい、癇癪を度々起こす、よく骨折する、食が細い、落ち着きがない、何事にも関心が薄い、感情の起伏が激しいなどの症状
2)ミネラル不足に注意 → マグネシウム、カルシウム、カリウム、亜鉛、マンガン、鉄などを土壌中から吸い上げた植物を食べることでミネラルを補給。ところが最近、田畑に堆肥など有機肥料を入れず、化学肥料を使うので、さらに土壌がやせる。
*ミネラルバランスの整う食事とは : 外食→ おうちごはんに、 洋食→ 穀菜食に 牛乳 → 豆乳(カルシウムとマグネシウムのバランスに優れている)に
市販のおにぎり → 無農薬の玄米の手作りおにぎりに ( 本物の美味しさに目覚める )
3)水にこだわる → 栄養素や酸素を運搬、尿・汗を排泄、体温調節、酸とアルカリの調節の働き
4)有害なものを避ける = 子どもから遠ざけたいワースト3 (食品パッケージを見て点検する)
①トランス脂肪酸 : マーガリン、ショートニング、植物油脂、加工油脂、ファットスブレッドなどに含まれる。
②砂糖:人工甘味料(スクラロース、サッカリン)、人工果糖=遺伝子組換作物)→骨折、虫歯、疲れ、記憶低下
③食品添加物:(発色剤)うつ・記憶障害疑いの亜硝酸ナトリウム、(調味料)片頭痛原因のグルタミン酸ナトリウム、(保存料)成長不順原因のソルビン酸、(人工着色料)発がん性疑いの赤色**号
という訳で、幼児期までの食が体と脳の初期設定レベル(一生の健康レベル)を決めるとのことです。
園長 野田 武